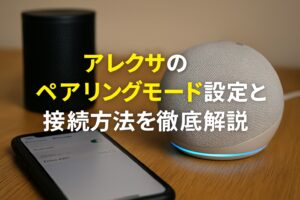Bluetoothスピーカーにマイクをつなぐ方法を知りたいと考えている方は、「スピーカーを拡声器として使うにはどうすればいいのか」「マイクの種類によって接続方法は変わるのか」など、さまざまな疑問を抱えていることでしょう。特に、ワイヤレスマイクを使いたい場面や、スマートフォンのマイクアプリを代用したいと考える人にとっては、適切なスピーカーにつなぐ方法や機材の選び方が重要になります。また、接続方法の違いによっては音が出ない原因になったり、Bluetooth遅延問題が生じるケースもあるため、基本から理解しておくことが必要です。本記事では、マイクの代わりになる選択肢や、接続ケーブルを含む各種手段の違いについても解説しながら、Bluetoothスピーカーにマイクを正しくつなぐ方法をわかりやすく紹介します。
- スピーカーを拡声器として使うためには
- マイクの種類と接続に適した機器の選び方
- ワイヤレスマイクとBluetoothの接続制限
- 音が出ない原因やBluetooth遅延の対処法
Bluetoothスピーカーにマイクをつなぐ方法とは
この章で解説する項目
- スピーカーを拡声器として使うには
- Bluetoothスピーカーで使えるマイクの種類
- ワイヤレスマイクをつなぐポイント
- Bluetoothスピーカーをスマホと繋げる方法は?
- ワイヤレス マイク接続方法の違い
- マイクをスピーカーにつなぐ方法
スピーカーを拡声器として使うには

スピーカーを拡声器として利用するには、単純に「マイクをつなげば音が出る」というものではありません。基本的に、スピーカーは「音声信号を増幅して出力する機器」であり、その入力として受け付ける信号は「ラインレベル」と呼ばれる一定の強さのものです。一方、マイクから出力される信号は「マイクレベル」と呼ばれる非常に小さな電気信号であり、これをそのままスピーカーに入力しても音量はほとんど上がりません。
そのため、スピーカーを拡声器として使いたい場合には、マイクとスピーカーの間に「マイクプリアンプ」や「ミキサー」を挟む必要があります。これらの機器は、マイクからの微弱な信号をラインレベルまで増幅し、スピーカーが正しく受け取れるように調整する役割を果たします。たとえば、ポータブルミキサーやマイクアンプと呼ばれる製品が市販されており、これらは持ち運びやすく、乾電池駆動のモデルもあるため屋外でも利用可能です。
また、スピーカー側に「マイク入力端子」があるかも確認すべき重要なポイントです。最近ではマイク入力を備えたBluetoothスピーカーも登場していますが、大半の製品は音楽再生用であり、マイク信号をそのまま入力できるようには設計されていません。スピーカーを拡声器として使いたい場合は、そうした機能を持った製品を選ぶ必要があります。
音声の遅延やノイズ対策も忘れてはなりません。特にBluetoothを使用した場合は、音声処理にタイムラグが発生しやすく、自分の声が遅れて返ってくることに違和感を感じる方も多いです。そのため、遅延を極力避けたいシーンでは、有線接続や専用のワイヤレス拡声システムを検討するのが無難です。
つまり、スピーカーを拡声器として機能させるには、マイクの信号を正しく変換・増幅する仕組みを理解し、対応した機器を選ぶことが不可欠です。
Bluetoothスピーカーで使えるマイクの種類
Bluetoothスピーカーで使用できるマイクの種類には制限があり、すべてのBluetoothマイクがそのまま接続できるわけではありません。そもそもBluetoothには「送信する側(親機)」と「受信する側(子機)」という役割があり、一般的なBluetoothスピーカーは子機、つまり音声を受信するだけの設計になっています。一方で、多くのBluetoothマイクも同様に音声を送信する子機であるため、両者だけでは接続が成立しません。
そのため、Bluetoothスピーカーと直接ペアリングできるマイクというのは、実際にはほとんど存在しません。使いたい場合は、スマートフォンやパソコンといった親機として機能する中継機器を使って、マイクの音声を一度デバイスに取り込み、そこからBluetoothスピーカーに出力する必要があります。この構成をとることで、Bluetoothマイクを間接的に使うことが可能になります。
また、Bluetoothマイク以外にも、「2.4GHz帯」や「UHF帯」などを使った独自方式のワイヤレスマイクも選択肢として考えられます。これらは専用の受信機とスピーカーをセットで使うことが前提となっており、Bluetoothではないものの、音声遅延が少なく実用性が高いケースもあります。
加えて、スマートフォンのマイクを使って音声を拡声するという方法もあります。マイクアプリを利用し、スマホとBluetoothスピーカーを連携させることで、擬似的な拡声器のように使うことが可能です。ただし、この方法では数百ミリ秒の遅延が発生することが多く、リアルタイムの会話用途には向かない点も認識しておきましょう。
したがって、「Bluetoothスピーカーで使えるマイク」は、技術的な制約と接続方式の理解が求められる分野であり、最も確実な方法は、スマートフォンなどを中継して利用するか、Bluetoothではない専用ワイヤレスマイクとスピーカーのセットを選ぶことです。
ワイヤレスマイクをつなぐポイント

ワイヤレスマイクを使ってBluetoothスピーカーから音を出したいと考える人は多いですが、その実現にはいくつかの技術的な壁があります。まず押さえておくべきは、Bluetoothスピーカーもワイヤレスマイクも、どちらも「受信専用(子機)」として機能する機器であるという点です。つまり、この2つを直接接続することは原則できません。間に「親機(送信機能を持つデバイス)」が必要になるのです。
最も現実的な方法は、スマートフォンやパソコンを中継デバイスとして使う構成です。ワイヤレスマイクの受信機をスマートフォンに接続し、そのスマートフォンからBluetooth経由でスピーカーに音声を飛ばす、という形になります。具体的には、スマホ用の外付けUSBマイクや、Lightning接続型のワイヤレスマイクの受信機を使う方法がよく選ばれます。このような構成をとることで、Bluetoothスピーカーから音を出すことが可能になります。
ただし、音声がマイクからスピーカーへ届くまでにはデジタル処理がいくつも挟まるため、0.5秒前後の遅延が発生します。このタイムラグは人によっては違和感が強く、自分の声が遅れて返ってくることで話しにくさを感じることもあります。そのため、遅延を極力避けたいのであれば、有線接続や専用ワイヤレスシステムを検討することが重要です。
また、ワイヤレスマイクを導入する際には、使用する電波帯や干渉対策も見逃せません。Bluetooth方式のほか、UHF帯や2.4GHz帯など複数の規格があり、それぞれ通信距離や安定性が異なります。使用環境に応じて、どの方式が適しているかを事前に確認しておくことで、トラブルを回避できます。
ワイヤレスマイクを快適に使いたいなら、「中継機器を活用する」「音声遅延を理解する」「電波帯と通信方式を選ぶ」この3つの視点を押さえることが成功のカギになります。
Bluetoothスピーカーをスマホと繋げる方法は?
Bluetoothスピーカーをスマートフォンと接続することは、音楽再生だけでなく、マイクアプリなどを活用して拡声器のように使いたい場合にも欠かせない手順です。接続方法そのものはそれほど難しくはありませんが、初めての方にとっては、設定のどこでつまずくのかが分からず困るケースがよくあります。
まず、スマートフォンの「設定」アプリを開き、「Bluetooth」項目をオンにします。続いて、Bluetoothスピーカーの電源を入れ、ペアリングモードにします。製品によっては、電源ボタンを長押ししたり、専用のペアリングボタンを押すことでペアリング状態に移行します。このとき、スピーカーのLEDが点滅するなどのサインが表示されるはずです。
スマホの画面上には、近くにあるBluetooth機器の一覧が表示されるので、該当するスピーカーをタップして選択します。「ペアリング完了」や「接続済み」などのメッセージが表示されれば、スマホとBluetoothスピーカーの接続は完了です。これでスマホの音声がスピーカーから出力されるようになります。
接続がうまくいかない場合は、いくつかの対策を試してみてください。例えば、スピーカーとスマホの距離を1メートル以内にする、Bluetoothを一度オフにして再度オンにする、スピーカーの電源を入れ直す、などの基本的な操作が効果的です。また、Bluetoothのペアリング履歴が複数残っている場合、干渉を避けるために不要な機器の登録を解除しておくのも良い手です。
なお、スマホとBluetoothスピーカーを接続してマイク代わりに使いたい場合は、専用の「マイクアプリ」の利用が必須となります。アプリを通じてスマホに向かって話しかけた音声が、Bluetoothスピーカーから出力される仕組みです。ただし、この方法には多少の音声遅延がつきものですので、用途に応じて使い分ける必要があります。
ワイヤレスマイク接続方法の違い

ワイヤレスマイクの接続方法にはいくつかの種類があり、それぞれ通信方式や用途、接続のしやすさに違いがあります。選択肢として代表的なものは「Bluetooth方式」「2.4GHzデジタル方式」「UHFアナログ方式」の3つです。それぞれの特徴を理解することで、使用目的に適したマイクを選ぶことができます。
まずBluetooth方式は、スマートフォンやパソコンとの連携を前提とした構成で、近距離かつ軽量な運用に向いています。Bluetooth接続に対応したマイクを使用することで、スマホでの録音、ストリーミング配信、マイクアプリとの併用が可能です。ただし、音声の遅延が比較的大きいため、リアルタイムでの会話や司会・講演にはあまり向きません。
一方、2.4GHzデジタル方式は、ワイヤレスマイクセットに受信機が付属しており、受信機をスピーカーやミキサーに有線でつなげるのが一般的です。この方式はBluetoothに比べて遅延が少なく、通信も比較的安定しているため、教室や会議室、イベント現場での拡声用途に適しています。また、PCやスマホ用のオーディオインターフェイスと組み合わせて使うことで、録音や配信にも対応可能です。
UHF(超短波)方式は、業務用や本格的なステージ用途に使われることが多く、電波の到達距離や干渉の少なさに優れています。専用の受信機とペアで運用され、設定や管理にはある程度の知識が必要ですが、安定性と音質の高さが魅力です。大規模なイベントやプロ用途で選ばれる理由がここにあります。
つまり、ワイヤレスマイクの接続方法は、「接続機器との互換性」「遅延の許容度」「通信の安定性」など、目的や環境に応じて適切な方式を選ぶ必要があります。見た目が似ていても、通信規格や構造が異なるため、購入前には必ず仕様を確認し、自分の使い方に合ったものを選ぶことが大切です。
おススメのワイヤレスマイクの一覧
「Bluetooth方式」Amazonの製品一覧
「2.4GHzデジタル方式」楽天市場の製品一覧
「UHFアナログ方式」楽天市場の製品一覧
マイクをスピーカーにつなぐ他の方法
マイクをスピーカーにつなぐには、両者の「信号レベルの違い」と「端子の規格」に注意を払う必要があります。マイクの出力は「マイクレベル」と呼ばれる非常に小さな信号で、スピーカーやオーディオ機器の多くが受け付ける「ラインレベル」とは大きな差があります。このため、直接つないでも音が小さすぎて聞こえなかったり、まったく出力されないことが多いのです。
基本的な接続方法としては、まずマイクから出た信号を「マイクプリアンプ」や「ミキサー」で増幅し、それをスピーカーの「AUX IN」や「LINE IN」端子に入力します。この構成にすることで、マイクの小さな信号をスピーカーが処理可能な大きさに変換し、適切な音量で出力できるようになります。
さらに、端子の形状にも気をつける必要があります。たとえば、マイク側がXLR端子で、スピーカー側が3.5mmステレオミニジャックであれば、専用の変換ケーブルやアダプターが必要です。ここで気をつけたいのは、端子の形状だけを合わせても、信号レベルが整っていなければ意味がないという点です。
また、Bluetoothスピーカーを使いたい場合には、マイクとスピーカーを直接つなぐのではなく、スマートフォンやパソコンといった中継デバイスを介して接続するのが現実的です。スマートフォンにマイクを接続し、専用アプリで音声を取り込み、その出力をBluetoothスピーカーに送るといった流れになります。
このように、マイクとスピーカーを正しくつなぐには、「信号の増幅」「端子の整合」「接続方式の適正化」といった複数の要素を考慮する必要があります。特に音響に不慣れな方は、マイク入力に対応したアンプ付きスピーカーを購入するのが、最も簡単で確実な方法といえるでしょう。
Bluetoothスピーカーにマイクをつなぐ際のポイント

この章で解説する項目
- マイクの代わりになるものは?
- マイクアプリの活用法
- 接続しても音が出ない原因
- Bluetooth使用時の遅延問題
- 接続ケーブルが必要な理由とは
- 最適な接続方法とは?
マイクの代わりになるものは?
「マイクが手元にないけれど、声を拡声したい」「とりあえず代用品で間に合わせたい」——そんなとき、マイクの代わりになるものはあるのでしょうか?実は、用途によっては代用できるものもいくつか存在します。ただし、すべての環境で理想的に動作するとは限らないため、それぞれの仕組みや制限を理解して使い分けることが重要です。
まず真っ先に候補に挙がるのが「スマートフォン」です。ほとんどのスマホには高感度の内蔵マイクが搭載されており、「マイクアプリ」や「音声入力アプリ」を使えば、スマホを簡易的なマイクとして使用することができます。Bluetoothスピーカーと接続すれば、音声を増幅して出力する拡声器のような使い方も可能になります。ただし、音声の遅延やハウリングの発生には注意が必要です。
次に挙げられるのが「ヘッドセット」や「イヤホンマイク」です。スマートフォン用のイヤホンには、マイクが付属しているものが多く、これを利用すれば通話用マイクの代わりに使うことができます。USB接続のヘッドセットならパソコンに直接接続するだけで、オンライン会議や録音にも対応できるため、多くの場面で実用的な代用品になります。
さらに、ノートパソコンに内蔵されたマイクも代用手段として活用可能です。ビデオ通話やウェブ会議などでは十分な音質を得られることもありますが、周囲の雑音を拾いやすいため、環境が静かであることが前提になります。
注意したいのは、こうした代用品はあくまで“簡易的な”手段であるということです。たとえばイベントやプレゼンなど、複数人に声をはっきり届ける必要がある場面では、指向性や音質、遅延などの面で専用マイクに劣ります。そのため、用途が一時的・限定的であれば代用品でも対応可能ですが、継続的に使う場合はやはりマイク機器の導入が望ましいといえます。
マイクアプリの活用法

マイクアプリは、スマートフォンを簡易的な拡声器やマイク代わりに使えるツールとして注目されていますが、その仕組みを正しく理解して使わなければ、想定通りの音声出力ができないことがあります。特にBluetoothスピーカーと組み合わせて使う際には、アプリの役割や制限を理解しておくことが重要です。
マイクアプリの基本的な仕組みは、スマホの内蔵マイクや接続された外部マイクから音声を取り込み、そのままスマホ本体のスピーカーやBluetooth接続先のスピーカーへリアルタイムに出力する、というものです。アプリ内では音量の調整やノイズの抑制機能が用意されていることもあり、ある程度の音声処理も可能です。これにより、簡易PA(パブリックアドレス)として利用したり、小規模な案内やプレゼンに使うこともできます。
活用シーンとしては、たとえば学校の授業中に声が通りにくい先生が使ったり、商業施設の店頭で案内をするスタッフが、スマホ+Bluetoothスピーカーを用いて短時間の説明を拡声する場面などが考えられます。アプリのUIもシンプルで、ボタン1つで「マイクON/OFF」の切り替えができるため、専門知識がない人でも直感的に操作できます。
ただし、デメリットとして挙げられるのが「音声遅延」です。音声信号が一度アプリで処理され、さらにBluetoothでスピーカーに送られるため、どうしても0.5秒前後の遅れが発生してしまいます。発声と音の出力にタイムラグがあると、話者本人が混乱してしまうことがあり、リアルタイムの会話や司会、講演には不向きです。
また、マイクアプリはバックグラウンド動作に制限があるものもあるため、他のアプリと併用しづらいケースもあります。加えて、アプリによっては広告表示があったり、音質の調整機能が不十分なこともあるため、自分の用途に合ったアプリを見極めて選ぶ必要があります。
つまり、マイクアプリは「一時的な補助ツール」としては非常に便利ですが、本格的な用途には制限があるため、使用環境や目的に応じて使い分けることが成功のポイントです。
以下は代表的なアプリです。
接続しても音が出ない原因
マイクとスピーカーを接続したのに音が出ない──このトラブルは初心者だけでなく、機材に慣れた人でも意外と起こりがちです。特にBluetoothスピーカーや汎用マイクを組み合わせたときに発生しやすく、原因を1つずつ確認することが解決への近道です。
まず確認したいのが、接続機器の信号レベルの不一致です。マイクから出力される音声は「マイクレベル」と呼ばれ、非常に微弱な信号です。これに対して、BluetoothスピーカーやAUX IN端子を備えた一般的なスピーカーは、「ラインレベル」の信号を想定して作られているため、そのままマイクを接続しても音量が極端に小さく、実質「音が出ない」と感じる状態になることがあります。この場合は、マイクプリアンプやミキサーを中継機器として挟む必要があります。
次に見落とされがちなのが、Bluetooth機器のペアリング状態です。スマートフォンやパソコンを介してBluetoothスピーカーに出力する構成では、「マイク→スマホ→Bluetoothスピーカー」という順序が前提になります。このどこかで接続がうまくいっていないと、音は出ません。特にアプリ上ではマイクが認識されていても、Bluetoothスピーカーが「出力デバイス」として正しく選ばれていないことが多々あります。
加えて、ケーブル類の断線や端子の接触不良も原因として無視できません。特に安価な変換アダプターや延長ケーブルを使っている場合、内部の断線により信号が正常に伝わっていないことがあります。接点のホコリや酸化も接触不良を引き起こすため、端子を清掃し、異常がないかを目視で確認するのも重要です。
最後に、スピーカー自体のボリュームや入力切替設定も見逃せません。スピーカー側の音量がゼロになっていたり、Bluetoothと有線が切り替え式になっていて正しい入力が選択されていなければ、いくら信号が届いていても音は出ません。
音が出ないときは「機材の役割と信号レベルの違い」「Bluetooth接続状況」「物理的な接点の不具合」「機器の設定ミス」といった視点から、段階的に確認していくことがトラブル解消の鍵となります。
Bluetoothが繋がらない時に参考にしたい記事はコチラからどうぞ
Bluetooth使用時の遅延問題

Bluetoothを使ってマイクの音をスピーカーに出力しようとすると、多くの場合に直面するのが「音声の遅延問題」です。これはBluetoothの技術的な仕様に起因しており、避けがたい現象として知られています。とくに拡声用途では、自分の声が数百ミリ秒遅れてスピーカーから聞こえてくると、話し手が混乱してスムーズに話せなくなることがあります。
この遅延はなぜ発生するのでしょうか。Bluetoothは、オーディオ信号を一度デジタル化し、圧縮・伝送し、受信側で再度展開して音声に戻すというプロセスを経ます。この一連の処理に少なからず時間がかかるため、リアルタイム性が損なわれます。特に、Bluetooth 4.0以前の規格やSBCという標準的なコーデックを使っている場合、遅延は200~300ms以上になることも珍しくありません。
近年は、aptX Low LatencyやLC3といった低遅延コーデックを使った製品も登場していますが、これらは送信側・受信側の両方が対応していなければ効果を発揮しません。つまり、スマホとBluetoothスピーカーの両方が同じ低遅延コーデックに対応していない限り、期待するほどの改善は見込めないのです。
さらに、Bluetoothスピーカーの種類によっても遅延の度合いは変わります。音楽再生用に設計されたスピーカーは、音質を優先するためにバッファ(信号の一時保管)を大きく設定していることがあり、その分だけ音が遅れて聞こえやすくなります。一方で、会議用やゲーミング向けなどの「低遅延設計」がなされた機器であれば、遅延をかなり軽減できます。
このように、Bluetooth使用時に発生する遅延は、マイクを拡声器として使いたい場合には大きなネックになります。声のズレが気になる場面では、有線接続や専用の無線マイクシステム(2.4GHz帯など)を選ぶほうが、ストレスなく運用できる選択肢となるでしょう。
接続ケーブルが必要な理由とは
マイクとスピーカーをつなぐ際に「接続ケーブルって本当に必要なの?」という疑問を持つ方も少なくありません。特にBluetoothなどのワイヤレス技術が浸透している今、ケーブル接続は時代遅れに見えるかもしれません。しかし、音響機器において接続ケーブルの役割は極めて重要で、むしろ多くの場面で欠かせない要素です。
最初に理解しておきたいのは、マイクから出る音声信号は「非常に微弱」な電気信号であるという点です。この信号は「マイクレベル」と呼ばれ、スピーカーがそのまま増幅して出せる「ラインレベル」や「スピーカーレベル」とは大きく異なります。そのため、マイクの信号をスピーカーで正しく再生するためには、適切なレベル変換が必要です。そしてこの変換を確実に行うためには、対応した「接続ケーブル」が不可欠なのです。
さらに、音質や安定性の観点からもケーブル接続は優位です。Bluetoothのような無線接続は便利ですが、どうしても電波干渉や遅延の影響を受けやすく、音が途切れたり、時間差で聞こえることがあります。一方、有線ケーブルであれば、物理的に信号を伝えるためノイズや遅延が極めて少なく、安定した音声出力が可能になります。
また、ケーブルの種類や仕様も重要です。たとえば、マイクがXLR端子でスピーカーが3.5mmステレオジャックであれば、変換ケーブルやミキサーなどの中継機器が必要になります。誤ったケーブルや互換性のない端子を使用すると、音が出ないだけでなく、最悪の場合は機器を破損するリスクもあります。
特に、スピーカー側の「AUX IN」や「LINE IN」がラインレベル専用である場合、マイクレベルの信号をそのまま入力しても音が極端に小さくなるか、まったく出力されません。このようなトラブルを防ぐためにも、信号レベルに合った機器構成と、それをつなぐ正しいケーブルが必要不可欠です。
つまり、マイクをスピーカーに正しく接続するには、「信号変換」と「安定伝送」のために、適切な接続ケーブルがなくてはならないということです。手間に見えるかもしれませんが、安心して確実に音を届けるためには、やはり有線接続の基本を理解することが重要です。
最適な接続方法とは?

マイクとスピーカーを組み合わせて使いたい場合、機器の種類や使用目的に応じて「最適な接続方法」は大きく異なります。選ぶべき構成は、「音質」「遅延」「安定性」「コスト」など、複数の観点から総合的に判断する必要があります。特にBluetoothスピーカーにマイクをつなぎたい場合、基本的な機材の制約を理解した上で接続方法を選ぶことが大切です。
もっとも汎用的で確実なのは「マイク→プリアンプ(またはミキサー)→有線スピーカー」という構成です。この方法なら信号の変換や音量調整がスムーズで、遅延やノイズの心配も最小限に抑えられます。プレゼンや店頭での案内など、安定した拡声を求められる場面では、この構成が理想的です。
一方、スマートフォンを中継機として利用する方法も有効です。マイクをスマホに接続し、専用アプリで音声を取り込み、Bluetoothスピーカーに出力する形です。この場合、機材が少なく、持ち運びも手軽ですが、Bluetoothの遅延やスマホアプリの仕様に依存する面があります。学校の授業や短時間の案内など、簡易的な運用には適しているものの、リアルタイム性が求められる用途には不向きです。
さらに、ワイヤレスマイクセットを使う方法もあります。これは送信機(マイク)と受信機(スピーカーやミキサーに接続)で構成されるもので、特にイベントやセミナーなど、広い空間での使用に適しています。Bluetoothではなく2.4GHzやUHFなどの通信方式を用いるため、遅延がほとんどなく、通信距離も比較的長いのが特徴です。ただし、機材の価格がやや高くなり、使用にはある程度の知識が求められます。
つまり、「最適な接続方法」は1つではなく、使用シーンに応じて最も適した手段を選ぶことが成功のポイントです。用途が限定的であればスマホ+Bluetoothでも対応可能ですが、継続的な使用や高い音質・安定性を求める場合には、有線や専用ワイヤレスシステムがより安心・確実な選択肢となります。
Bluetoothスピーカーにマイクをつなぐ方法のまとめ
- スピーカーはラインレベルの信号しか受け付けない
- マイクの信号は非常に微弱なマイクレベルで出力される
- 拡声にはマイクプリアンプやミキサーが必要
- マイク入力端子付きスピーカーを選ぶと手間が省ける
- 多くのBluetoothスピーカーとBluetoothマイクは直接接続できない
- スマートフォンやPCを中継することでBluetoothマイクが使える
- 2.4GHzやUHF方式のワイヤレスマイクは遅延が少なく実用的
- マイクとスピーカーの端子形状に注意が必要
- 音が出ない原因の多くは信号レベルの不一致
- マイクアプリを使えばスマホを簡易マイクにできる
- Bluetoothは音声遅延があるためリアルタイム用途には不向き
- 接続ケーブルは信号変換と安定した伝送に不可欠
- 使用目的により有線・ワイヤレス・中継の方法を使い分ける
- 最適な接続方法は用途・機器・環境により異なる
- マイク代用品は存在するが長期利用には不向き
おススメのワイヤレスマイクの一覧
「Bluetooth方式」Amazonの製品一覧
「2.4GHzデジタル方式」楽天市場の製品一覧
「UHFアナログ方式」楽天市場の製品一覧